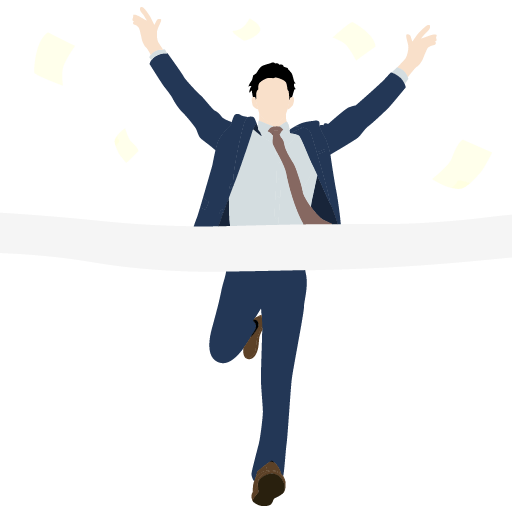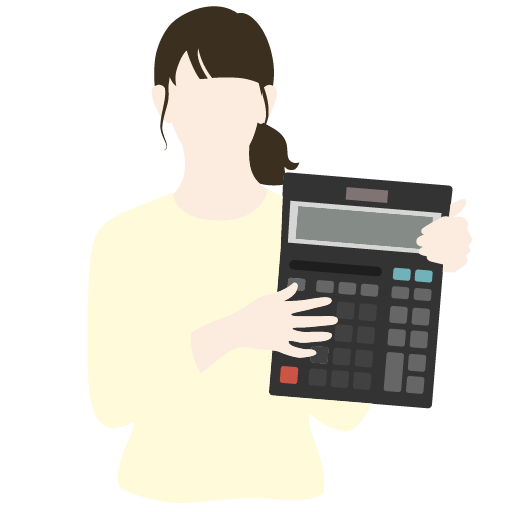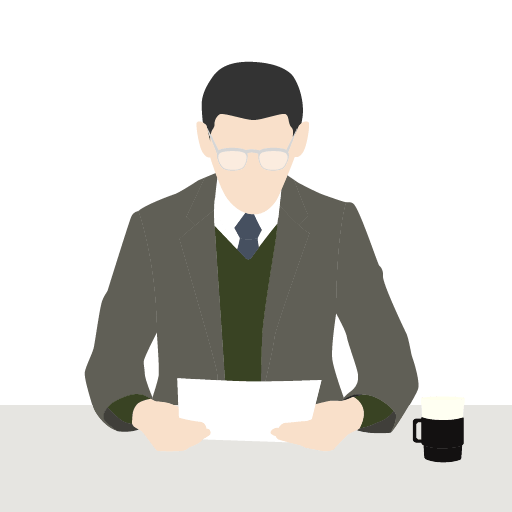こんな悩みはありませんか?
- 手軽に株式投資に挑戦してみたい
- 単元未満株、株式ミニ投資(ミニ株)、株式累積投資(るいとう)の違いが知りたい
株式投資は、通常100株単位で取引を行うため、銘柄によっては数百万円からしか購入できず、なかなか手が出しづらいです。
特に株式初心者からすれば、最初から大きな資金を投じるのはリスクでもあり、出来れば小さい資金で株式投資に挑戦したいものです。
そこでおすすめなのが1株単位で購入できる「単元未満株」や、10株からの「ミニ株」、定期的に積み立てる「るいとう」です。
少ない資金から株式投資に参加しながら、配当を得る権利がもらえるので、株式投資を手軽に始めたい人には非常におすすめです。
この記事では、単元未満株、株式ミニ投資(ミニ株)、株式累積投資(るいとう)の特徴や違いを解説します。
それでは、本編をどうぞ!
目次
単元株制度とは
単元株制度とは、会社により定められた一定の株数(単元)を持つことで、株主総会で議決権の行使等を認める仕組みです。
株主の権利は、議決権を行使する権利と、配当を受け取ったり、株式分割を受ける権利に分かれます。
2018年10月から、上場企業の単元は100株に統一されました。
銘柄によって異なりますが、単元株を購入するだけでも、数百万円の資金が必要になる場合があります。
| 証券コード | 企業名 | 最低購入金額 |
| 9983 | ㈱ファーストリテイリング | 91,730円×100株=9,173,000円 |
| 6273 | SMC㈱ | 68,200円×100株=6,820,000円 |
| 7974 | 任天堂㈱ | 65,730円×100株=6,573,000円 |
| 6861 | ㈱キーエンス | 58,770円×100株=5,877,000円 |
| 8035 | 東京エレクトロン㈱ | 40,680円×100株=4,068,000円 |
※Yahoo!ファイナンス 単元株価格上位を参照(2021年度1月11日15:23時点)
単元株を購入すると、議決権の行使など経営に参画できるようになりますが、特に経営に参画したい訳でもなければ、単元株未満で購入するといいでしょう。
単元未満の株を購入する方法は、以下の3つがあります。
- 単元未満株
- 株式ミニ投資(ミニ株)
- 株式累積投資(るいとう)
では、3つの株式について解説していきます。
単元未満株、ミニ株、るいとうの違い
単元未満株、株式ミニ投資(ミニ株)、株式累積投資(るいとう)は、単元株未満で株式を購入できるという意味で同じですが、それぞれ特徴が異なります。
| 項目 | 単元未満株 | 株式ミニ投資(ミニ株) | 株式累積投資(るいとう) |
| 概要 | 最低1株から99株の範囲で購入できる投資方法 | 単元株制度(100株)から1/10で購入できる投資方法 | ドルコスト平均法を用いて、株式を購入する投資方法 |
| 対象銘柄 | ほぼすべての上場銘柄 | 証券会社の指定銘柄のみ | 証券会社の指定銘柄のみ |
| 手数料 | 通常取引より高め | 単元未満株より高め | 売買手数料以外に、委託手数料や口座管理費が発生する |
| 株式名義 | 株主 | 証券会社 | 証券会社 |
| 配当金 | 受け取れる | 証券会社が配分したあとに受け取れる | 次月の購入資金として回される |
| 売買回数 | 1日1~3回 | 1日1回 | 毎月1回 |
| 株主優待制度 | 単元株に到達すればもらえる | もらえない | もらえない |
単元未満株
単元未満株とは、証券会社を通じて、最低1株から99株までの範囲で購入できる株式です。
単元未満株は、議決権がないものの、購入株式数に対する配当を受ける権利を有しています。
ただし、株主優待については、企業が定めた株数に達していないともらえません。
1株から株式優待をつけている企業もありますが、多くの企業は1株で株主優待を受けられません。例えば、「100株持っている株主に、10,000円相当の優待」と企業が定めていた場合、その企業の権利付き最終日までに100株に達していれば株主優待の権利がもらえます。
1株の保有で、株主優待を取得できる権利のことを、隠れ株主優待と呼びます。
単元未満株の株主優待
例えば、サカイ引越センター(9039)では、1株以上で、30%引越割引券(1枚)が配布されます。(2020年1月11日現在 auカブコム証券参照)
単元未満株は全ての証券会社で購入できる訳でなく、LINE証券、SBIネオモバイル証券、Paypay証券、SBI証券、マネックス証券、岡三オンライン証券、野村證券で取引できます。
SBI証券なら「S株」、マネックス証券なら「ワン株」、auカブコム証券なら「プチ株」などと呼ばれていますが、全て単元未満株を指します。
また、LINE証券やSMBC日興証券のように低額であれば手数料無料の証券会社や、他の証券会社も基本的に手数料は低価格です。
SBIネオモバイル証券の売買手数料は、月間で50万円以下の取引で200円です。
株式ミニ投資(ミニ株)
株式ミニ投資とは、証券会社を通じて単元株の10分の1で購入できる投資方法です。「ミニ株」とも呼ばれています。
上場企業の場合は10株から購入可能で、最低購入額は10万円です。
株式ミニ投資の場合は、株式の名義は証券会社になります。そのため、配当金を受け取る際も、証券会社が配分した金額を受け取ります。
また、株主優待制度も基本的に受け取れません。しかし、換金性が可能な優待制度については、証券会社が配分したあとに受け取ることができます。
ここがポイント!
単元未満株でも株主優待制度を実施している銘柄でも、株式ミニ投資で購入うした場合は優待制度を受けることができません。
株式累積投資(るいとう)
株式累積投資とは、毎月一定の金額で同じ株式を購入する投資方法です。「るいとう」とも呼びます。
毎月1万円という少額から始められるので、株式を積立投資で購入するイメージです。
毎月一定の金額を決めて株式を購入する投資手法をドルコスト平均法と呼びますが、るいとうでメジャーな手法です。
対象銘柄の株価が安いときは多めに株を購入し、株価が高いときは少なめに株を購入する等、自動的に購入株数を調整することで、長い目でみて平均買付単価を引き下げるテクニックです。
また、配当金は基本的に再投資に回されるため、複利で運用していきます。
るいとうの注意点として、ネット証券で取引が行えず、店舗窓口やコールセンター経由で取引ができる大手の証券会社のみが扱っていることが多いです。
そのため、売買手数料は割高になります。
大和証券だと、売買手数料だけではなく、委託手数料や口座管理料(年間税込3,300円)などの費用が発生するといったデメリットもあります。
単元未満株のデメリット
注文方法が成行注文に限定されている
単元未満株の注文方法は、基本的に成行注文だけです。
指値注文のように希望価格で売買できないため、希望通りの株価で約定できない可能性があります。
売買銘柄が限られる
単元未満株は、ほぼ全ての銘柄を選択できるものの、ミニ株やるいとうは証券会社が決められた銘柄しか購入できません。
例えば、SBI証券やマネックス証券だと、ミニ株は約3,500銘柄から選択でき、大和証券のるいとうは、約2,700銘柄の中から選択できます。
銘柄が限られているので、希望の銘柄がみつからない可能性があります。
さいごに この記事が30秒で理解できる
本記事では、少額資金から始められる株式投資について解説しました。
少額の資金から株式投資を始めれる方法として、単元未満株、株式ミニ投資(ミニ株)、株式累積投資(るいとう)の3種類があります。
3種類についてまとめると、以下の通りです。
| 項目 | 単元未満株 | 株式ミニ投資(ミニ株) | 株式累積投資(るいとう) |
| 概要 | 最低1株から99株の範囲で購入できる投資方法 | 単元株制度(100株)から1/10で購入できる投資方法 | ドルコスト平均法を用いて、株式を購入する投資方法 |
| 対象銘柄 | ほぼすべての上場銘柄 | 証券会社の指定銘柄のみ | 証券会社の指定銘柄のみ |
| 手数料 | 通常取引より高め | 単元未満株より高め | 売買手数料以外に、委託手数料や口座管理費が発生する |
| 株式名義 | 株主 | 証券会社 | 証券会社 |
| 配当金 | 受け取れる | 証券会社が配分したあとに受け取れる | 次月の購入資金として回される |
| 売買回数 | 1日1~3回 | 1日1回 | 毎月1回 |
| 株主優待制度 | 単元株に到達すればもらえる | もらえない | もらえない |
これから株式投資を始める人にとっては、手始めに単元株未満で取引することがおすすめなので、上記3種から選択するといいでしょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。