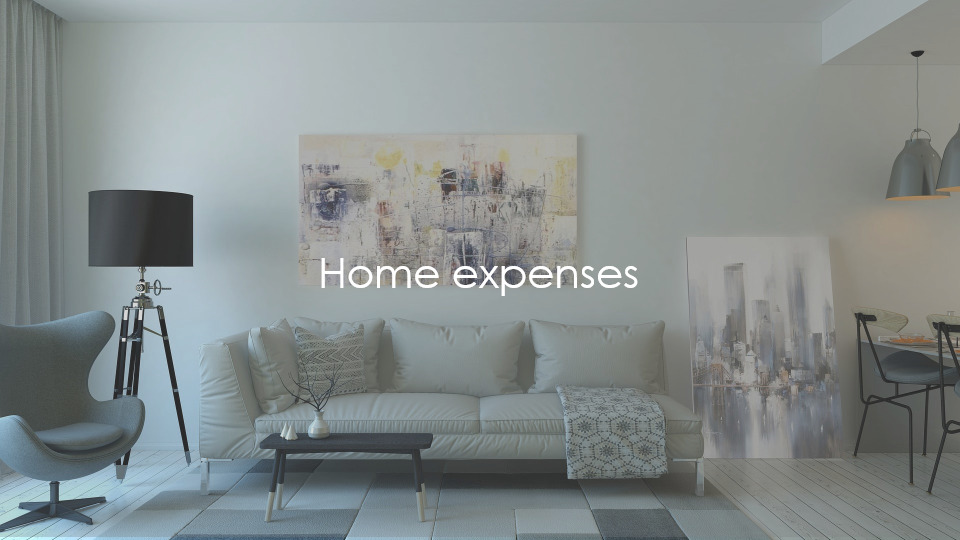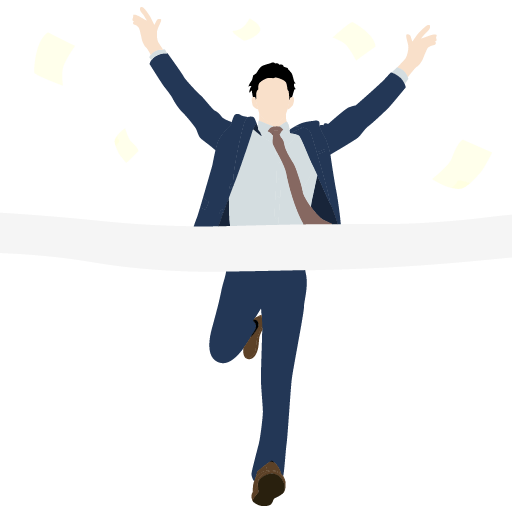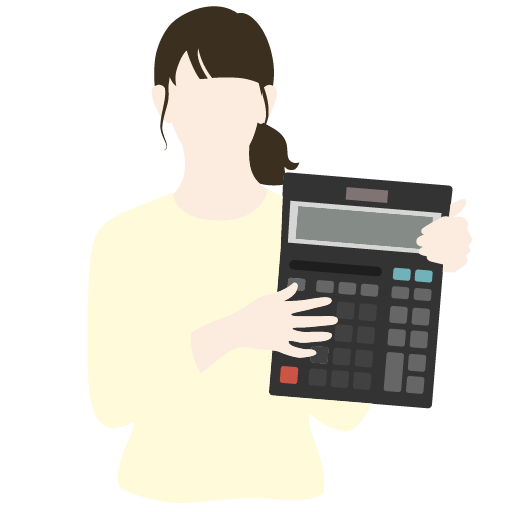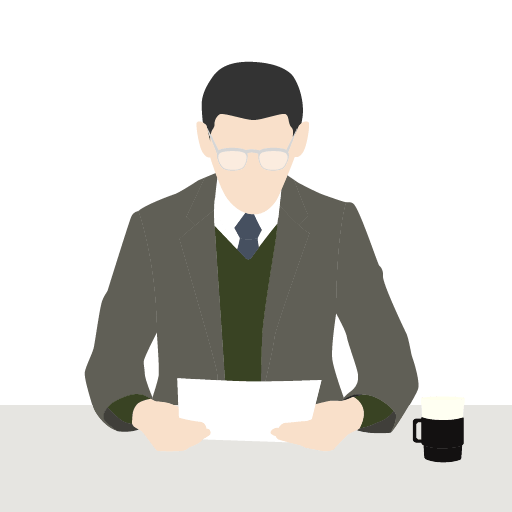こんな悩みはありませんか?
- 自宅で事業をするときに何を経費にできるかしりたい
- 家事按分の比率や計算方法が知りたい
自宅で事業を行う個人事業主や法人は、家賃や通信費、水道光熱費の一部を事業に使っているとして経費計上できます。しかし、自宅で生活と事業を兼ねているため、全額を経費計上することは、税務上できません。
家賃や通信費、水道光熱費を経費計上する際には、生活で使っている範囲と事業で使っている範囲を客観的にわける「家事按分」という考え方を使います。
この記事では、家事按分に該当する経費や、その目安について解説します。
目次
家事按分の対象となる支払いは?
家事按分の対象となる支払いは、以下のものがあります。
- 地代家賃:家賃・更新料、住宅の減価償却費、住宅ローンの金利、火災保険料
- 水道光熱費:電気代、水道代、ガス代
- 租税公課:固定資産税、自動車税、車庫証明手数料
- 通信費:インターネット回線使用料、携帯電話代
- 賃借料:土地や建物以外のレンタル料、会議スペースのレンタル代
- 消耗品費:価格が10万円未満の物品、試用期間が1年未満の物品
- 工具器具備品:価格が10万円以上の減価償却する備品
- 修繕費:備品の点検費・メンテナンス費、修理費
- 車両費:車検費用、修理代、ガソリン代、駐車場代、保険料
- 車両運搬費:運搬に必要で減価償却する物品
- 新聞図書費:新聞雑誌代、セミナー参加費
- 交際費:取引先への接待、カフェなどでの打ち合わせ代
家賃や水道光熱費、通信費などの生活に欠かせない費用から、新聞図書費、交際費なども家事按分の対象となります。
特に交際費は、1人や家族・友人と外食した際は生活費となりますが、取引先との打ち合わせなどの場合は事業費となります。
家事按分の目安(具体例)
家賃按分には目安があります。細かい規定はなく「客観的にみて正当なこと」が目安です。ここでは具体例を示します。
家事按分は、具体的に決められた比率がないので、事業主が自ら按分比率を決めることができます。その自由度がかえって難しいといわれる所以です。
ここに注意!
按分比率は事業主自らが決めますが、例えば「インターネット事業」を行っていて、家賃の按分比率を生活20%:事業80%とする等、明らかにおかしい按分比率は税務調査で指摘される可能性があります。あくまで常識的な按分比率である必要があります。
家賃
家賃を家事按分する方法は、「作業時間から按分する方法」「作業面積から按分する方法」の2種類があります。
「作業時間から按分する方法」は、自宅で作業している時間を家賃全体から割る方法で「作業面積から按分する方法」は、家の総床面積に対して事業を行っている範囲を割る方法です。
具体的に、自宅兼作業場の家賃が12万円、賃貸面積60㎡の場合を例に按分してみます。
まずは、月の作業時間から按分する方法です。
作業時間から按分する計算例
1日の作業時間が8時間、月20日勤務の場合...
1ヶ月の作業時間は 8時間 × 20日 = 160時間
作業時間の割合は 160時間 ÷ 720時間(24時間×30日)× 100 = 28%
経費にできる割合は 12万円 × 28% = 3.36万円
この例だと12万円に対して、3.36万円が経費となります。
次に作業面積から按分する方法です。
作業面積から按分する計算例
自宅の面積60㎡のうち作業場として面積20㎡を使用の場合...
作業場の割合は 20㎡ ÷ 60㎡ × 100 = 33%
経費にできる割合は 12万円 × 33% = 4万円
この例だと4万円が経費となります。
上記の通り、金額的に「作業面積から按分する方法」が約6千円高くなりました。この場合、どちらも客観的にみて正当であれば、高くなる方を選ぶべきです。つまり、この例では月4万円を経費にできる「作業面積から按分する方法」を選ぶことがおすすめでしょう。
水道光熱費
水道光熱費も、基本的には家賃と同じように「作業時間から按分する方法」「作業面積から按分する方法」のいずれかで求めます。
ただし、水道光熱費のうち「電気」に関しては、コンセントの数によって計算する方法もあります。コンセントの数は、家にあるコンセント全てのうち、事業で使っているコンセントを計算する方法です。
いずれにせよ家賃の計算同様、客観的にみて高くなる方法を選択することが最良です。
通信費
通信費も家事按分できます。もっともわかりやすく計算するためには、生活用のスマホやPCと、事業用のスマホやPCをわけることです。
とはいえ、個人事業主や零細企業でスマホ自体をわけて2契約するのは、コスト的に厳しいのも正論です。
そのため、「作業時間から按分する方法」により通信費を按分するのが主流です。なにを事業用に計上するか難しいところですが、事業用のやりとりをメールやLINEで残しておくことが大切です。
自動車関連費
自家用車を営業用として利用してる場合は、駐車代金、ガソリン代、自動車税、車検代など経費にできます。按分の方法としては走行距離を目安に、生活費と事業費を按分します。自動車で移動する場合は、それが事業用だと証明できるような証拠を準備しておくといいでしょう。
家事按分の注意点
不適切な按分は追加徴税される
按分比率に正当性がないと、税務調査により厳しく罰せられる可能性があります。以下のような例では、按分が不適切と判断され、追加で税金を徴収される可能性があります。
- 事業主本人の判断で生活費を経費計上している
- 按分の基準が客観的でなく、明らかに多く経費計上している
- 事業所得を少なく計上し、納税額を少なくしている
- 税務調査時に指摘を受け、過去3年〜5年分を全て修正申告する
- 修正申告により所得が増え、所得税以外にも住民税や国民健康保険料を支払う
確定申告を行ったからといって、費用が経費として認められたわけではありません。経費計上が認められたかどうかは、税務調査後に判断できます。
青色申告と白色申告の条件の違い
青色申告と白色申告では、家事按分の条件が異なります。青色申告では「取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」の家事関連費は経費として計上できます。業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、資産の利用状況等を総合して判定します。
なんとなくこのくらいなら大丈夫と主観的な判断をせず、きちんと取引の記録を残し業務上必要と説明できれば、按分の比率に限らず経費にすることができます。
その一方で、白色申告の場合は青色申告の条件に加えて、さらに注意すべき点があります。それは業務・仕事にあたる割合がおおむね50%を超えている家事関連費のみが経費にできるということです。例えば仕事場がメインで、そこで生活もしているような人が対象となるでしょう。
ただし、証明が困難な場合があるので、できるだけ青色申告をした方が良いでしょう。白色申告に比べると手続きが難しくなりますが、家事按分以外にも税金において優遇されることが多いです。
さいごに この記事が30秒で理解できる!
個人事業主の方などが自宅で仕事をする場合に、生活費の一部を事業費扱いとし、経費計上することができます。その時に、生活費と事業費を客観的に区別するための考え方を家事按分と言います。この比率は事業主の裁量で決めることができますが、比率の根拠をきちんと説明できるようにしなければなりません。
青色申告では按分の比率に限らず経費にすることができますが、白色申告では業務にあたる割合がおおむね50%を超えないと経費計上できません。
家事按分にできる支払いには、家賃、電気代、水道光熱費、通信費、自動車関連費など多岐に渡ります。ただし、共通していることは事業に必要な費用であり、その根拠が示せるものに限ります。家賃や通信費など、全てを経費にするという間違った按分をしないように注意しましょう。